秋冬の季節になるとよく耳にするマイコプラズマ肺炎。
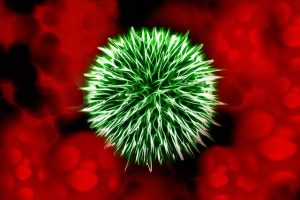
幼稚園や保育園・小学校に通う幼児や子供がかかることが多いです。
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという細菌やウイルスに近い微生物によって感染する感染症であり、感染してから発症までの期間(潜伏期間といいます)は約2~3週間だと言われています。
症状の現れ初めは風邪と症状が似ているため、お医者さんでも判断が難しいようです。
そんな厄介なマイコプラズマ肺炎ですが、今回はその症状と注意点についてお話ししますね。
マイコプラズマ肺炎の症状

マイコプラズマ肺炎に感染しても約2週間~3週間は潜伏期間なので、これといって症状が出ません。
そのあと、初期の症状として38度台の発熱、頭痛、身体のだるさ、といった症状が出てきます。この発熱などがどのくらい続くか、症状の程度に関しては個人差があり、熱はないけれど頭痛を強く訴える子もいれば、逆に頭痛は全くない場合もあります。
これらの発熱や頭痛といった初期症状から2日程度遅れて、今度は咳がでます。この咳、最初は「コンコン」という軽い咳なのですが、日を追うごとに段々ひどくなって、痰が出てきたり、胸の痛みに繋がったりしていきます。
また、マイコプラズマ肺炎を引き起こす微生物(病原体)が消化器に侵入してしまうことで嘔吐、下痢といった消化器系の症状が出る場合もあります。
合併症として中耳炎を起こした場合には、耳を痛がる子もいるようです。
◆以下の動画では、マイコプラズマ肺炎の全体像や感染経路などここでは触れていないことを教えてくれているので知識を深めたい方はぜひご覧になってください。
鳥取県民チャンネルコンテンツ協議会:健康ぷらざ:マイコプラズマ肺炎(2015.2.15)
幼児がかかったとき注意することは?

先ほどのべた症状からも分かるように、マイコプラズマ肺炎にかかったばかりの時は、風邪と似たような症状が出ます。また、程度も個人差があるので、最初は体が少しだるい、少し頭が痛い、微熱があるなあ、といった程度で見過ごしてしまいがちです。
しかし、このまま放っておくと、どんどん重症化し肺炎が悪化してしまうこともありますし、気管支炎、じんましん、中耳炎、副鼻腔炎といった合併症につながってしまいます。
そのため、いつもの風邪の症状が少し重そう、消化器系の症状が出てきそう、乾いた咳を頻繁にしている、といった状態であれば、早めに医療機関へ行くことを強くおすすめします。
消化器系の症状に関しては、嘔吐でもしない限りなかなか発見が難しいと思われます。子供は自分の症状をうまく表現できないからです。
「お腹痛くなったりしない?」「気持ち悪くない?」というように、マイコプラズマ肺炎を疑うような発熱等があれば、保護者の方から問いかけてあげると良いでしょう。
早めに対策をすれば、重症化や合併症になることはありません。
まずは予防として、手洗いとマスクに除菌ですね。
|
◎あの時期です、送料無料 マイコプラズマ肺炎が大流行中※ 除菌スプレー&詰め替え… |
まとめ
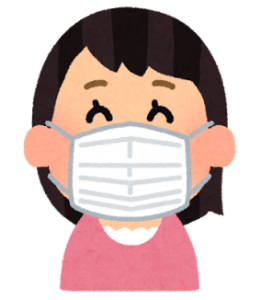
今回は、マイコプラズマ肺炎の症状および注意点についてお話ししました。初期症状が風邪に酷似しているため、見極めが難しく、重症化すると中耳炎や気管支炎などにもつながってしまう、厄介な感染症なのでしたね。
マイコプラズマ肺炎の病原体は、感染しやすいものの、熱に弱く、石鹸でも除菌できてしまう程度のものだとされています。
そのため、こまめな手洗いやマスクを徹底し、感染の疑いがある人とは1m以上の距離をとるように心がけてください。
子供は特に免疫力が弱いので、保護者の方が気にかけたり、手洗いを促してあげるようにしてくださいね。もちろん大人もかかる病気なので、家族みんなで予防して元気に冬を乗り越えましょう。
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](http://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/1557c95d.d9fd2f8d.1557c95e.672bbf19/?me_id=1242752&item_id=10000006&m=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faquavinus%2Fcabinet%2Faqua%2F10000006-1.jpg%3F_ex%3D80x80&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Faquavinus%2Fcabinet%2Faqua%2F10000006-1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)